2009年07月01日 23:29
『「ほめる・しかる」・・・「20代男子」戦力化マニュアル』
昨日、私なりの読書について書きましたが、
今日は、最近、よつばプロデュースの渡邉さんに
推薦いただいた本の紹介をします。
とても読みやすく、興味深く、為になる本でした。
『「ほめる・しかる」で部下を劇的に伸ばす!「20代男子」戦力化マニュアル』というタイトルの本で、
カラオケのシダックス・コミュニティー株式会社で部下育てにおいて実績・業績を残して独立した
人材育成のコーチで“叱りの女王”と言われる、齋藤直美 氏が書いた本です。
(ちなみに私と同い年。岡崎市出身)。

読んでみて思ったのは、男子・女子に関係なく言えるのではないかなということです。
20代男子に、というより、それを超えて、人との関わりすべてに言えることだとも思いました。
本の中では、20代男子のことが、“「ゆとり教育」の中でおっとり育った彼ら”とか
“今どき社員”と表現されていました。
でも、読んでいて、自分が上司としてなってない、ということを発見して反省したり、
自然にやっていたなと思うこともあって、へこんだり勇気付けられたりしました。
「ゆとり教育」・・・思えば、高校生のときに、
“土曜日を休日にすることについてどう思うか”というテーマで、
何かの授業でディスカッションしたことがありました。
私たちの年代からあと、土曜日も休日になり、「ゆとり教育」と言われ始めました。
そして、気がついたときには、「ゆとり教育の弊害」が言われるようになりました。
そんな、自分たちとは違う教育を受けて育った彼らを戦力にする難しさと、
その方法と、丁寧にもコミュニケーションをとるときのNGシーンとOKシーンが書いてありました。
この、NGシーンとOKシーンがまたおもしろく且つ勉強になりました。
たとえば・・・
「なぜ、その仕事をしなくてはならないのか」という目的を示すことより
上司の背中から学べ、とか、言わないとわからないようではダメという思想を持つ
上司の方もまだ多いのではないかと思いますし、
自分自身もそういう面があるかもしれません。
しかし、最近私は特にこの「目的を示す」ことを
とても大切なことだと思っていて、とても共感できました。
目的を示し、その目的を遂行できる環境・舞台を用意する・・・
そういうことが自分の仕事だと思っています。
この本に掲載されていた
●NGシーン。
「K社の、鈴木部長のところに納品の連絡入れておいて」
これがNG。
一見「なぜこれがNG?」と思いますが、OKシーンを読むと、深く納得できます。
自分が納得できるわけなので、スタッフも同じことです。
これをスタッフに言ってあげられたら、とてもいいなと思います。
●OKシーン。
「K社の、鈴木部長のところに納品の連絡入れておいてくれないかな。
きょうは、K社への初めての納品なんだ、先方も心配しているかもしれない。
いま、納品に向かったという一報を入れておけば安心するだろう。
そういう小さな連絡を入れることで、信頼が高まると思うよ」
指示や命令の目的や価値がわかると、やる気も出ますよね。
私たち広告業者は、お客様から広告原稿について指示を受けることがたくさんありますが、
指示の意味がわかると俄然やる気が出ますし、提案するアイディアも湧いてきます。
別の本で読んだ、ある経営者の方が言っていた8つの“社長に必要な資質”のうちのひとつ・・・
「精神的な余裕を失わない」。
余裕・ゆとりがないと、OKシーンができないな、と関連付けて思いました。
ここ2年くらい、特にここ1年は、スタッフに対して腹を立てるということはまずなくなりました。
以前はよくありました(^^;
いろんな人の話を聴き、いろんな本を読み、いろんな体験をし、
自分が悪かったなあと思いスタッフに感謝するようになって、いろんなことが変わりました。
会社は、社長の器以上にはならない-----。
自分の器が「ちいさーっ!」と思うことがよくあり、ひとり愕然としていたりします。
気がついたら、何か行動して変えていかないといけません。
本からも、たびたび刺激を受けています。
良い本、おもしろい本、ためになる本を薦めて下さるお客様に感謝です。
今日は、最近、よつばプロデュースの渡邉さんに
推薦いただいた本の紹介をします。
とても読みやすく、興味深く、為になる本でした。
『「ほめる・しかる」で部下を劇的に伸ばす!「20代男子」戦力化マニュアル』というタイトルの本で、
カラオケのシダックス・コミュニティー株式会社で部下育てにおいて実績・業績を残して独立した
人材育成のコーチで“叱りの女王”と言われる、齋藤直美 氏が書いた本です。
(ちなみに私と同い年。岡崎市出身)。
読んでみて思ったのは、男子・女子に関係なく言えるのではないかなということです。
20代男子に、というより、それを超えて、人との関わりすべてに言えることだとも思いました。
本の中では、20代男子のことが、“「ゆとり教育」の中でおっとり育った彼ら”とか
“今どき社員”と表現されていました。
でも、読んでいて、自分が上司としてなってない、ということを発見して反省したり、
自然にやっていたなと思うこともあって、へこんだり勇気付けられたりしました。
「ゆとり教育」・・・思えば、高校生のときに、
“土曜日を休日にすることについてどう思うか”というテーマで、
何かの授業でディスカッションしたことがありました。
私たちの年代からあと、土曜日も休日になり、「ゆとり教育」と言われ始めました。
そして、気がついたときには、「ゆとり教育の弊害」が言われるようになりました。
そんな、自分たちとは違う教育を受けて育った彼らを戦力にする難しさと、
その方法と、丁寧にもコミュニケーションをとるときのNGシーンとOKシーンが書いてありました。
この、NGシーンとOKシーンがまたおもしろく且つ勉強になりました。
たとえば・・・
「なぜ、その仕事をしなくてはならないのか」という目的を示すことより
上司の背中から学べ、とか、言わないとわからないようではダメという思想を持つ
上司の方もまだ多いのではないかと思いますし、
自分自身もそういう面があるかもしれません。
しかし、最近私は特にこの「目的を示す」ことを
とても大切なことだと思っていて、とても共感できました。
目的を示し、その目的を遂行できる環境・舞台を用意する・・・
そういうことが自分の仕事だと思っています。
この本に掲載されていた
●NGシーン。
「K社の、鈴木部長のところに納品の連絡入れておいて」
これがNG。
一見「なぜこれがNG?」と思いますが、OKシーンを読むと、深く納得できます。
自分が納得できるわけなので、スタッフも同じことです。
これをスタッフに言ってあげられたら、とてもいいなと思います。
●OKシーン。
「K社の、鈴木部長のところに納品の連絡入れておいてくれないかな。
きょうは、K社への初めての納品なんだ、先方も心配しているかもしれない。
いま、納品に向かったという一報を入れておけば安心するだろう。
そういう小さな連絡を入れることで、信頼が高まると思うよ」
指示や命令の目的や価値がわかると、やる気も出ますよね。
私たち広告業者は、お客様から広告原稿について指示を受けることがたくさんありますが、
指示の意味がわかると俄然やる気が出ますし、提案するアイディアも湧いてきます。
別の本で読んだ、ある経営者の方が言っていた8つの“社長に必要な資質”のうちのひとつ・・・
「精神的な余裕を失わない」。
余裕・ゆとりがないと、OKシーンができないな、と関連付けて思いました。
ここ2年くらい、特にここ1年は、スタッフに対して腹を立てるということはまずなくなりました。
以前はよくありました(^^;
いろんな人の話を聴き、いろんな本を読み、いろんな体験をし、
自分が悪かったなあと思いスタッフに感謝するようになって、いろんなことが変わりました。
会社は、社長の器以上にはならない-----。
自分の器が「ちいさーっ!」と思うことがよくあり、ひとり愕然としていたりします。
気がついたら、何か行動して変えていかないといけません。
本からも、たびたび刺激を受けています。
良い本、おもしろい本、ためになる本を薦めて下さるお客様に感謝です。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。


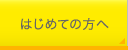

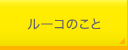



















ゆとり教育もあるかも知れませんが、どの時代にも世代間ギャップはありえて、逆もしかり。今求められるマネジメントや部下育成は個々の良い所を伸ばして上げることで、弱点も気付かせることから始まるかなと。
子育ても同じで、情熱は必要ですね。
そうですね。
「個々の良いところを伸ばす」
それが上司の仕事ですね。
「子育てと同じで情熱は必要」とは
伊藤さんらしいです…
まさしくその通りですね。
ありがとうございます。